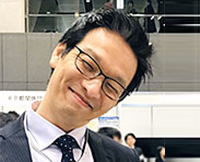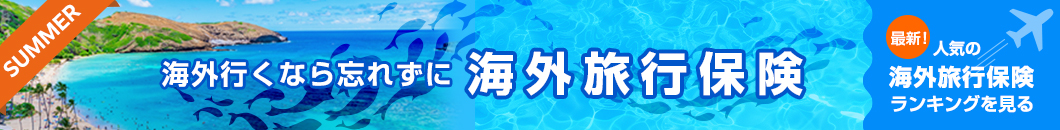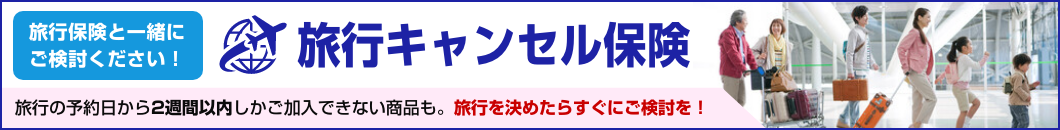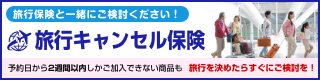1年間にかかった医療費が所定額を超えたときに、所得税を軽減できる医療費控除では、子どもの医療費の一部も対象になります。なかには、大人では対象にならないものの、子どもでは対象になる医療費もあります。
子どもの医療費控除の対象について解説します。
記事の目次
子どもの医療費控除は基本的に大人と同じ
医療費控除は、入院や通院でかかった医療費や治療に必要な医薬品の購入費などが対象になります。公的な保険がきく診療のほか、自費診療の一部にも対象になるものがあり、基本的な対象範囲は大人と同じです。
ただし例外的に、大人では通常対象外であるものの、子どもにかかった場合には医療費控除の対象になる費用もあります。
大人と違う、子どもなら対象になる医療費
子どもにかかった場合に限り医療費控除の対象になる費用は、おもに次のものです。
歯列矯正の費用
歯列矯正の治療費は大人の場合、基本的に医療費控除の対象になりません。しかし、発育途中の子どもの場合は正常な歯並びにするための治療とみなされ、医療費控除の対象になります。
なお、歯列矯正は自費診療のため治療費が高額な傾向があります。歯科ローンやクレジットカードで支払うこともありますが、治療費部分は医療費控除の対象になります。ただし金利・手数料は対象外です。
治療のためのメガネ代
近視や遠視を矯正するための眼鏡代は、通常は医療費控除の対象にはなりませんが、医師の治療上で必要な場合に限り対象になります。
子どもの場合は視力が未発達のため、遠視の子どもが弱視になるのを防ぐためにかける眼鏡は治療の一環とされ、処方箋があれば医療費控除の対象になります。
この場合、レンズ代のほかフレーム代も、プラスティックやチタンなど一般的に使用される材料のものであれば医療費控除の対象です。
通院に付き添う大人の交通費
入通院のためにかかった交通費は原則として本人が利用した電車代やバス代、緊急時のタクシー代などが対象で、付添人の交通費は対象外です。しかし一人で通院できない子どもで親などの同伴者が必要な場合には、本人のほか同伴者の交通費も対象になります。
ただし子どもが入院していて、世話のために父母が通院するなど、子ども本人が通院していないときの交通費は医療費控除の対象になりません。
医療費助成で無料になった診療費は医療費控除できる?
子どもの場合、市区町村による医療費助成制度(子ども医療費助成、乳幼児医療費助成など)によって、医療費の自己負担が抑えられることがあります。
子どもの年齢、地域、入院か外来かなどによって一部異なりますが、窓口で負担する医療費が無料になる場合も少なくありません。
医療費控除は実際に負担した医療費が対象ですので、子ども医療費助成などで無料になった医療費は控除の対象外です。
子どもを扶養している場合には、1年間の医療費額などをまとめた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)に、本人のほか扶養家族にかかった医療費もまとめて記載されることがあります。
ここに記載される医療費には自治体による助成が反映されていないことがありますが、実際にその金額を負担していない場合には、医療費控除の計算では除くことになっています。
医療費控除できる子どもの年齢や条件は?
医療費控除は、納税する人本人や生計が同じ家族のために支払った医療費が対象になります。
親と同居している子どものほか、一人暮らしをして別居している子どもでも、仕送りなどを受け取って生計が同じ子どもであれば、親の医療費控除に子どもの医療費を含めて計算することができます。
生計が同じかどうかが基準になり、子どもの年齢によって医療費控除の対象有無が変わることは基本的にはないようです。
ただし、上記のように子どもに限り医療費控除の対象になる医療を受けた場合、治療のためであるかどうかや、通院に付き添いが必要かどうかの判断が年齢により変わることもありますので、具体的なケースについては税務署などに相談してみるといいでしょう。
医療費控除を申告すると親の税軽減になることも
医療費控除には生計が同じ子どものために支払った医療費を含めることができます。
上限はありますが、一般的には医療費の金額が大きいほど控除額が大きくなりますので、納税する本人だけでなく、子どもの医療費を含めて計算すると、控除額が大きくなることもあるかもしれません。
特に歯列矯正や眼鏡などの費用は高額になることがありますから、上手に活用して税の軽減につなげたいですね。
※2025年1月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は最寄りの税務署窓口にご確認ください。
出典:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
出典:国税庁「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」
出典:国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。