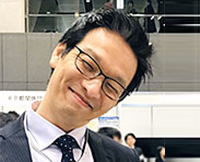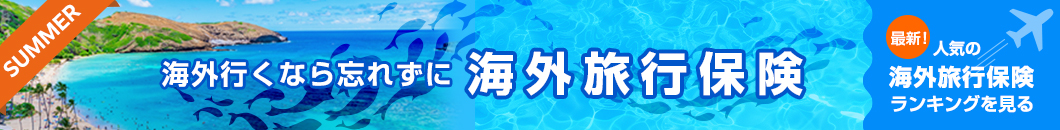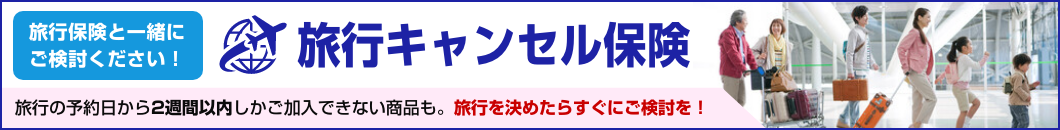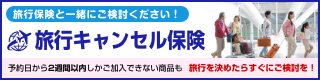子どもの具合が悪くなって病院を受診したとき、多くの場合は医療費の自己負担が大幅に軽減されるか、無料になります。これは、公的な医療費の補助制度があるためです。
子どもの医療費のしくみについて解説します。
記事の目次
子どもの医療費は無料になる?
国の医療費制度では、6歳までは自己負担2割、6歳からは3割が基本です。
しかし実際には、受診したときに請求される医療費はそれよりも抑えられることが多いです。
これは、所定の年齢までは子どもにかかる医療費に対して、自治体の補助があるためです。
すべての都道府県と市区町村では、乳幼児や子どもにかかる医療費の助成制度を導入しています。
入院、通院それぞれについて、各自治体が定めた年齢までは医療費が補助され、自己負担が一部軽減されるか、ゼロになります。
ゼロであれば、家計が負担する医療費は無料ということになります。
市区町村における医療費助成の一部自己負担
実施市区町村数:1,741
(単位:市区町村)
| 一部自己負担 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 自己負担なし | 1,266 | 1,358 |
| 自己負担あり | 475 | 383 |
出典:こども家庭庁「令和6年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」」
医療費は何歳まで無料?
補助の対象になる年齢は、都道府県の補助は通院が就学前(6歳年度末)まで、入院が中学生(15歳年度末)までの地域が最も多くなっています。
高校生までの地域が最も多い
また、市区町村の補助は入通院ともに高校生(18歳年度末)までの地域が最も多くなっています。
自治体における医療費助成の実施状況
実施市区町村数:1,741
(単位:市区町村)
| 通院 | 入院 | |
|---|---|---|
| 就学前 | 12 | 1 |
| 9歳年度末 | 0 | 0 |
| 12歳年度末 | 11 | 12 |
| 15歳年度末 | 263 | 223 |
| 18歳年度末 | 1,448 | 1,490 |
| 19歳年度末 | 0 | 1 |
| 20歳年度末 | 4 | 5 |
| 22歳年度末 | 3 | 3 |
| 24歳年度末 | 0 | 6 |
出典:こども家庭庁「令和6年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」」
無料になる医療費はどこまで?
子どもの医療費助成の対象になる医療費は、保険がきく診療費や薬剤費の自己負担分です。
ただし、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等など、公的医療保険の対象にならないものは、補助されません。
医療費助成に所得制限がある地域も
自治体の医療費助成には、一部、所得制限が設けられている地域もあります。
所得制限のある地域では、所得が一定額を超えていると補助を受けられません。また、所得制限に該当するかを確認するために、課税証明書などの書類提出が必要なことがあります。
市区町村における所得制限
実施市区町村数:1,741
(単位:市区町村)
| 所得制限 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 所得制限なし | 1,645 | 1,643 |
| 所得制限あり | 96 | 98 |
出典:こども家庭庁「令和6年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」」
子どもの医療費補助を受けるには「医療証」が必要
補助を受けるには、地域で発行される子ども用の医療証が必要です。
子どもが生まれたときや引越しで転入したときに市区町村で発行手続きをします。
これを医療機関の受診時に保険証とともに窓口に提示することで、請求される医療費が抑えられます。
保険証によって自己負担が2~3割になり、また、医療証を提示することで自己負担分から補助分が差し引かれます。
受診時に保険証や医療証を忘れると、全額または自己負担分の医療費が請求されます。
受診当日は請求された額を支払いますが、後日に地域の窓口で払い戻しの手続きをすると、補助分の医療費が還付されます。
医療証は更新・切替えがある
子どもの医療証は、1年ごとなど定期的に更新されるのが一般的です。
また、子どもの就学時など年齢によって補助内容が変わるときには、医療証の切替えもあります。
自治体の医療費助成制度の概要(一例)
| 制度の名称(一例) | 対象 |
|---|---|
| 乳幼児 医療費助成制度 |
小学校入学前までの乳幼児
※6歳児は有効期間が3月31日まで |
| 義務教育就学児 医療費助成制度 |
小学生、中学生 ※15歳児は有効期間が3月31日まで |
| 高校生等 医療費助成制度 |
高校生等(15歳の4月1日から18歳の3月31日) |
出典:各自治体の情報をもとに筆者作成
※助成制度の名称や内容は、自治体によって異なります。
住んでいる地域の補助制度を確認して、子どもの医療費に備える
子どもにかかる医療費は、このように公的な制度によって自己負担が抑えられるしくみがあります。
補助の対象になる年齢までは、家計での子どもの医療費負担が高額になることはそれほど多くないでしょう。
地域によっては、制度が見直されて補助の対象になる年齢が拡大されたり、所得制限が緩和されたりすることもあります。
お住まいの地域で、公的な医療保障制度でどこまで補助されるのかを理解しておくことが大切です。
公的な補助制度のしくみをふまえて、子どものもしもの病気やケガへの備えについて考えられるといいですね。
※2025年3月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。
出典:こども家庭庁「令和6年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」」
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。