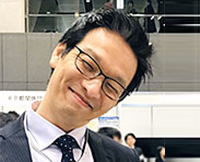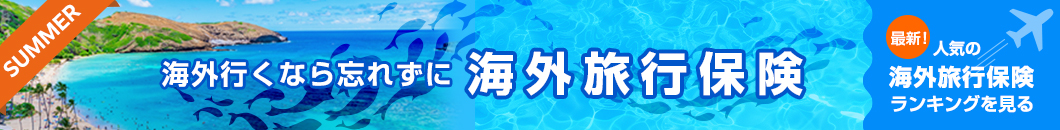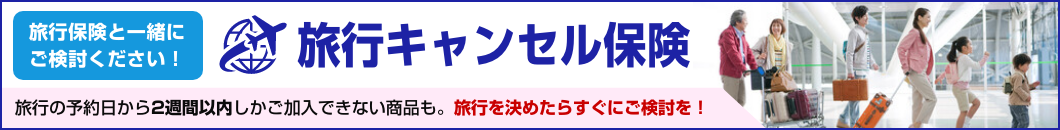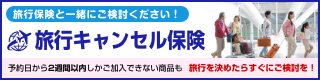医療費の負担が高額になったときに活用できる医療費控除では、一部の市販薬も対象になります。また、要件を満たすと薬局やドラッグストアで購入した市販薬が対象になる医療費控除の特例もあります。
対象になる市販薬の一覧や申告方法などについて解説します。
記事の目次
市販薬で医療費控除を受けられる
市販薬のうち特定の医薬品については、要件を満たすと年間12,000円を超えた金額(最高88,000円)を医療費控除の対象にできる「セルフメディケーション税制」という特例※1があります。
この制度では「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる、病院などで処方される薬から転用された医薬品が対象です。2024年12月現在、スイッチOTC医薬品は約2900品目、非スイッチ医薬品は約4300品目が対象になっています。
特例とは別の通常の医療費控除も病院などでの入院費用や通院費用のほか、薬局で購入する処方薬や一部の市販薬も対象になります。
どちらの制度でも市販薬が対象になりますが、種類によりどこまで対象になるか、細かな範囲が異なります。
ここでは医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」で対象になる市販薬や控除を受けるための条件、申請方法を説明します。
医療費控除の対象になる市販薬は?
対象になる医薬品の一覧は、厚生労働省のホームページ※2で確認できます。また薬のパッケージやウェブサイトの販売画面などにマークがついています。
なお、医薬品には副作用のリスクなどによる第1類、第2類、第3類といった分類もありますが、この分類がどこまで医療費控除の対象になるかを表すわけではありません。
具体的な医薬品が対象になるかどうかは、個別に確認してみましょう。

出典:日本一般医薬品連合会「知ってトクする!セルフメディケーション税制」
特例の対象になるおもな市販薬一覧
医療費控除の特例の対象になるのは、所定の有効成分を含み、医療用から転用された医薬品です。
胃腸薬や頭痛薬、風邪薬、鼻炎薬などの内服薬のほか、虫刺されのかゆみ止めや痛み止めの湿布薬にも、対象になるものがあります。
胃腸薬・整腸剤・便秘薬
- 大正胃腸薬G
- タナベ胃腸薬<調律>
- ビューラック・ソフト
- ピコラックス など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
頭痛薬・痛み止め
- イブクイック頭痛薬
- ナロンエースT
- バファリンプレミアム
- リングルアイビー
- ロキソニンS など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
風邪薬・咳止め
- エスタックイブ
- コルゲンコーワIB錠TXα
- パブロンS錠
- パブロンSせき止め
- ベンザブロックIP
- 新ルルAゴールドDX
- ルルアタックEX など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
目薬
- キューピーコーワiプラス
- サンテFXAL
- ヒアレインS
- マイティアアイテクト など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
虫さされ薬・かゆみ止め
- 近江兄弟社メンタームEXアルファクリーム
- ムヒアルファEX
- メンソレータム メディクイック軟膏R
- リンデロンVsクリーム など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
アレルギー・鼻炎薬
- アレグラFX
- アレジオン20
- コンタック鼻炎Z
- ストナリニ Zジェル
- ロートアルガード鼻炎内服薬ゴールドZ など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
湿布など外用薬
- アンメルツ ゴールド EX
- エアーサロンパスDX
- サロンパスEX
- フェイタス5.0
- ロキソニンEXゲル
- ロキソニンEXテープ など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
その他
- アリナミンEXゴールド など
出典:厚生労働省「対象品目一覧」(2024年12月1日現在)
医療費控除を受けるための条件は?
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
また、市販薬の購入費のみが対象になる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を適用するには、その年に予防接種や定期健康診断、がん検診、特定健康診査のいずれかを受診しておくことも要件です。
引用:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
医療費控除の申告方法は?
確定申告では医療費の明細書を確定申告書に添付して申告します。特例を使って市販薬の購入費を医療費控除の対象とする場合も、通常と申告方法はほぼ同様です。通常の確定申告の手順は下記の記事を参考にしてみましょう。
ただし、通常の医療費控除と特例では医療費の明細書の書式が異なります。また、併用はできませんのでどちらかひとつを適用します。
市販薬への医療費で税の軽減ができる
一般的に医療費控除を利用するのは医療費の自己負担が高額になったときですが、市販薬を含めると意外と身近に利用できることがあります。
自分の医療費だけでなく、生計が同じ家族の医療費や市販薬を含めるとさらに税の控除を受けられる可能性も広がります。しくみを知って、上手に活用したいですね。
※2024年12月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は最寄りの税務署窓口にご確認ください。
※1 出典:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
※2 出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。