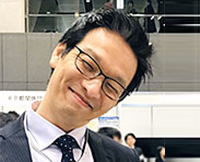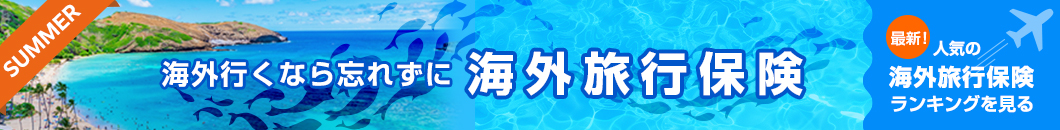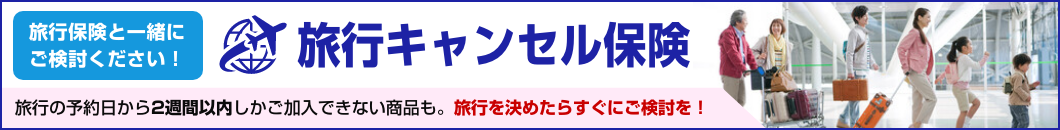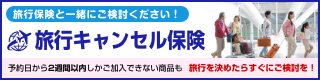75歳以上の人は、公的な医療保険として後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度の内容や自己負担割合、保険料について解説します。
記事の目次
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の人が加入する公的な医療制度です。
高齢者では病気やケガなどで医療費がかかる傾向があり、国民全体でかかる医療費(国民医療費)に占める割合が高いため、現役世代とは別の制度で運営されています。
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は各都道府県の広域連合という団体が運営しています。財源の5割は公費(税金)が充てられています。
また、現役世代が加入する健康保険や国民健康保険の保険料(支援金)から4割、高齢者の人が納める保険料からは1割が充てられています。
後期高齢者医療制度の自己負担割合
医療機関を受診したときの医療費の自己負担割合は、基本的に1割です。一定以上の所得がある人は2割、現役並みの所得がある人は3割になっています。
高額療養費制度で自己負担を抑えられる
自己負担1~3割で支払った医療費が高額になったときには、1ヶ月の負担が所定の上限額(自己負担限度額)までに抑えられる「高額療養費」というしくみもあります。
上限額を超えた医療費を自己負担した月には、超えた金額が払い戻されるため、実質的な負担額が抑えられます。
自己負担限度額は所得(年収)や、医療費が入院によるものか、外来によるかなどによって決まります。
年金収入などで一般的な所得水準(年収156万円~約370万円)の場合、自己負担限度額は1ヶ月・世帯あたり57,600円です。
うち、外来でかかった医療費については、個人ごとに18,000円が上限です。
これを超えた医療費を自己負担したときに、高額療養費として、制度からお金が戻ってきます。
70歳以上の高額療養費の自己負担限度額
※はみ出ている場合、横にスクロールできます。
| 所得区分 | 1ヶ月の自己負担限度額 (世帯ごと) |
多数回該当の場合 |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 年収約770万~ 約1,160万円 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 年収約370万~ 約770万円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 年収156万~ 約370万円 |
57,600円 うち外来(個人ごと): 18,000円(年144,000円) |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 うち外来(個人ごと):8,000円 |
ー |
| 住民税非課税世帯 (年金収入80万円 以下など) |
15,000円 うち外来(個人ごと):8,000円 |
ー |
※高額療養費の自己負担限度額は、70歳以上の人と75歳以上の人(後期高齢者)で共通です。
後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、各都道府県(広域連合)によって決まります。
(1)被保険者全員が負担する均等割部分と、(2)所得に応じて負担する所得割部分の、大きく2つが含まれます。
2024年度の保険料額は全国平均で年額84,988円(均等割と所得割の合計額)です。保険料は、2年ごとに見直されます。
世帯の所得が一定以下の場合には、均等割部分の一部が軽減されます。また、所得割部分には保険料の限度額があり、高所得者であっても保険料が限度額(2024年度の場合、年額80万円または73万円)を超えないことになっています。
公的制度を活用して医療費の負担軽減を
75歳以上の高齢者の人の医療費は、後期高齢者医療制度によって自己負担が抑えられるしくみになっています。
また、高額療養費制度によって、入院費用や通院費用などが高額になったときに1ヶ月の医療費の負担を軽減できるようにもなっています。
高齢期には病気やケガなどで医療費の負担が増すことがありますが、こうした公的制度のしくみを知っておくと、受診時に医療費の心配を防げるかもしれません。
※2024年9月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は加入先の保険制度窓口へご確認ください。
出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。