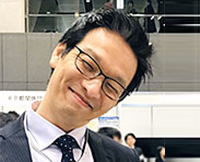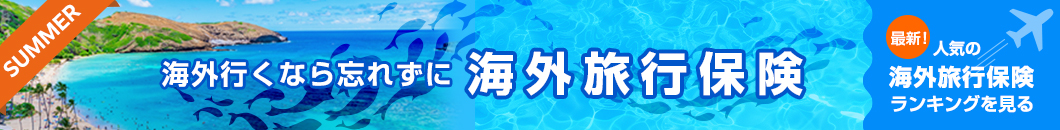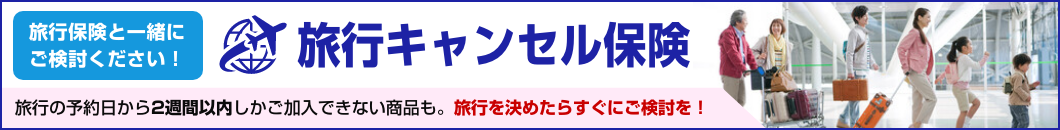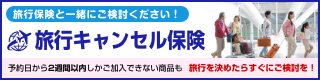入院や手術をするときには、外来での通院時とはお金のかかり方も違ってきます。急な入院や手術の場合にはすぐにお金を支払えるか、心配になることもあるかもしれません。
お金の手続きや支払い方法は基本的に各病院のルールによりますが、一般的な流れについて解説します。
記事の目次
入院費用はいつ払う?
病気やケガで入院をしたときには、入院診療費や食事代、差額ベッド代、寝具などのレンタル代、テレビカード代などの費用がかかります。では、こうした費用はいつ払うものなのでしょうか?
入院費用の支払い方法や支払い手続きは、各病院のルールによって定められています。入院の目的や緊急性、入院期間などの個別事情によって異なることもあるようですが、一般的には退院時または入院中に支払うのが基本です。
入院費用の支払い時期
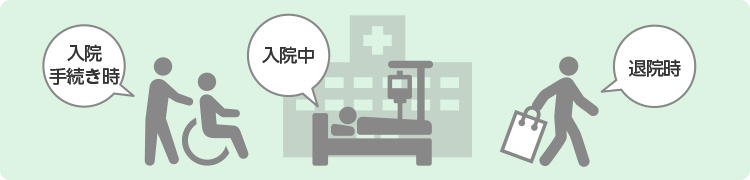
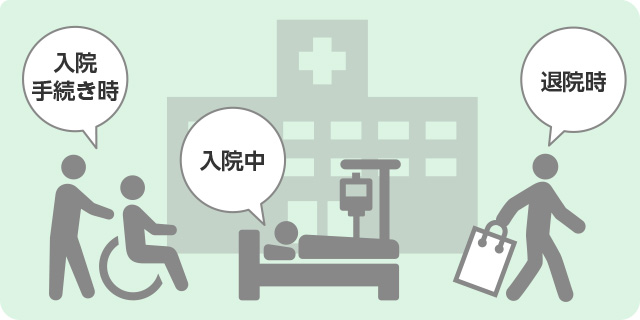
退院時に支払う場合
入院期間が1ヶ月以内など短期間の場合には、入院費と入院中にかかった診療費や差額ベッド代などの費用を、まとめて退院時に支払うことが多いようです。
入院中に支払う場合
入院期間が長期間にわたる、月をまたぐ場合などには、入院中に支払うこともあります。月末締めで翌月に請求書が発行され、入院中の病室に届くといった流れになるようです。
入院時に保証金などの前払いが必要なことも
病院によっては、入院時に費用の支払いについて連帯保証人を立てたり、保証金を前払いしたりするところもあります。
入院手続きをする窓口でクレジットカードを提示しておく、病院所定の金額を預り金や入院保証金といった形で支払い、事前に入院費の支払いを保証するものです。
退院などで請求額が確定した際には、実際にかかった入院費用と前払い済の金額を精算して請求されます。
入院費用の支払い方法は?
入院費用の支払い方法は現金の他に、病院によってクレジットカードや銀行振込み、現金書留や郵便為替などに対応しています。病院の精算窓口や自動支払機などで支払います。
原則として病院が設定する支払期日までに支払いますが、必要に応じて分割払いや後払いなどの相談に乗ってもらえることもあるようです。
入院費用が高額になると公的制度で自己負担を軽減できる
入院費用のうち、診療費など公的な健康保険の対象になるものは原則として自己負担割合が1~3割に抑えられていますが、それでも入院期間が長期にわたったり手術や検査をしたりしたときには、請求額が高額になることがあります。
公的な健康保険制度ではそのようなときに、1ヶ月の自己負担額が所定額を超えると、超えた分が補助される「高額療養費」という制度があります。
加入している健康保険であらかじめ手続きをしておくと、病院での請求時にはじめから高額療養費を差し引いてもらえる「限度額適用認定証」を利用することもできます。この場合、入院費用を支払う時の負担が少なくすみます。
民間保険のなかには入院給付を早めに受け取れるものも
民間の保険会社が提供する医療保険・医療保障のなかには、入院中や入院前に給付金を受け取れるものがあります。
入院初期でも受け取れる給付金
通常、病気やけがでの入院を保障する保険は退院をした後に、病院に発行してもらう診断書などを保険会社に提出して給付金請求の手続きをしますが、入院していることがわかる必要書類がそろっていれば、入院途中でも請求手続き可能な場合があります。
入院当初の費用の負担が重いときや、いつ退院するか決まっていないときにも、早めに保険の給付を受け取り、入院費用の支払いに充てることができます。
特約などで「入院初期給付金」のような保障が付いている場合には、入院期間が短期間でも、日数にかかわらず5日分や10日分など一律に決まった金額が給付される保険もあります。退院前でまだ入院日数が確定していない段階でも、所定の書類をそろえれば給付を受けられる場合もあるようです。
入院費用の前払いサービス
また、一部の保険会社では、入院をする前でも所定の要件を満たし、必要書類を提出すれば給付金を事前に受け取れる「入院費用前払いサービス」を提供しています。
入院費用を準備するうえでは、病院にいつ支払わなければならないかとともに、加入している保険でいつ受け取れるかも確認しておくといいのではないでしょうか。
病院に医療費の支払いについて相談できることも
入院や手術をしたときには高額な医療費がかかるうえ、入院の身の回り品や付きそう家族の交通費など、日常にはない出費がかかるものです。
保証金の前払いなど、すぐにお金を用意しなければならないこともありますが、大規模な病院などでは、入院費用の支払い方法や期日などについて相談に乗ってもらえる窓口を設けているところがあります。
支払いが難しいときには、相談してみてもいいかもしれません。
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。