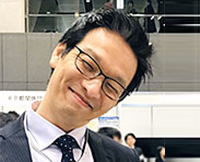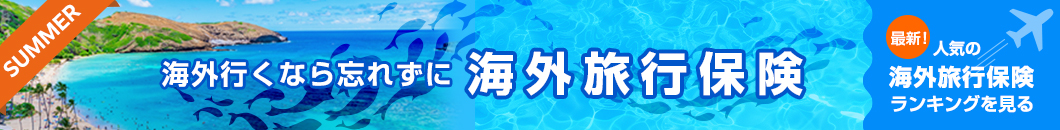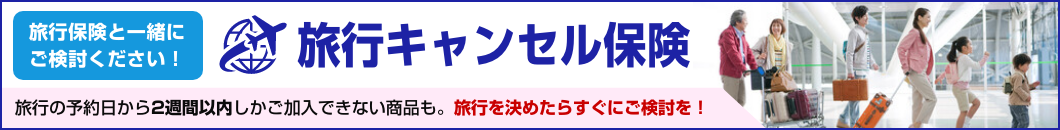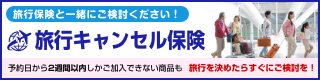入院や手術をしたり、ひんぱんに通院をしたときなどには、医療費の負担が高額になることがあります。そんなときに負担を軽減できる制度が、高額療養費制度です。
高額療養費で医療費がいくら戻ってくるか、いつ返ってくるかなど、制度のしくみについて解説します。
記事の目次
医療費が戻る高額療養費制度とは
高額療養費は、1か月にかかった医療費の自己負担が所定の限度額を超えると、超えた部分が戻ってくる制度です。
高額療養費制度のしくみ


高額療養費の対象になる医療費
高額療養費の対象となるのは、公的保険がきく診療費です。
保険診療であれば、入院費用や手術費用だけでなく、外来・通院でかかった診療費や歯科治療費も対象になります。
ただし、入院中の食事代や差額ベッド代、保険がきかない自費診療、先進医療は対象外です。
たとえば、出産時の帝王切開手術は保険診療のため高額療養費の対象になりますが、インプラントや歯科矯正などは、歯科治療の中でも自費診療扱いとなることがほとんどですので、高額療養費の対象にはなりません。
高額療養費でいくら戻る?
高額療養費制度で戻ってくる金額は、1ヶ月に自己負担した医療費のうち、所定の限度額を超えた部分です。
限度額は年齢と所得などによって異なり、それに応じていくら戻ってくるかが決まります。
自己負担限度額(69歳以下)
69歳までの人は、所得(年収)に応じて世帯ごとの限度額が5段階にわかれています。
たとえば年収が約370~約770万円の人の自己負担限度額は1ヶ月・世帯あたり「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」となっています。
かりに1か月の窓口負担額が30万円(健康保険負担分を含めた10割では100万円)だった場合には、この計算式により自己負担限度額は87,430円になりますので、30万円のうち自己負担限度額を超えた212,570円が高額療養費として戻ってきます。
医療費100万円で窓口の負担(3割)が30万円の場合(年収約370万円~770万円、3割負担の場合)


※1 高額療養費:30万円‐87,430円=212,570円
※2 自己負担上限額:80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
家族で同じ健康保険に加入していれば、1ヶ月に21,000円以上(受診者別、医療機関別、入院・通院別)かかった自己負担は合算して、計算することができます。
また、1年間に医療費が高額になる月が3回以上になれば、4回目からの自己負担限度額が下がる「多数回該当」というしくみもあります。
高額療養費の自己負担限度額(69歳以下)
※はみ出ている場合、横にスクロールできます。
| 所得区分 | 1ヶ月の自己負担限度額 (世帯ごと) |
多数回該当の場合 |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 年収約770万~ 約1,160万円 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 年収約370万~ 約770万円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| ~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
自己負担限度額(70歳以上)
70歳以上の人は、所得(年収)や医療費が入院によるものか、外来によるかなどによって自己負担限度額が決まります。
年金収入などで一般的な所得水準(年収156万円~約370万円)の場合、自己負担限度額は1ヶ月・世帯あたり57,600円です。うち、外来でかかった医療費については、個人ごとに18,000円が上限です。
これを超えた医療費を自己負担したときに、高額療養費として、制度からお金が戻ってきます。
高額療養費の自己負担限度額(70歳以上)
※はみ出ている場合、横にスクロールできます。
| 所得区分 | 1ヶ月の自己負担限度額 (世帯ごと) |
多数回該当の場合 |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 年収約770万~ 約1,160万円 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 年収約370万~ 約770万円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 年収156万~ 約370万円 |
57,600円 うち外来(個人ごと): 18,000円(年144,000円) |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 うち外来(個人ごと):8,000円 |
ー |
| 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下 など) |
15,000円 うち外来(個人ごと):8,000円 |
ー |
高額療養費はどうやって返ってくる?
高額療養費は、どのように戻ってくるのでしょうか。申請方法や受け取り方法は、加入している健康保険の種類によって異なります。
健康保険組合の場合
おもに大企業の会社員などで健康保険組合に加入している場合は、自分で払い戻しの申請手続きをしなくても、高額療養費が戻ってくるところが多いようです。
この場合、医療機関の受診時に窓口で保険証を提示すると、いつ、いくらかかったかなど医療費の情報が健康保険組合に共有され、自分で申請をしなくても勤務先の会社で高額療養費の計算や払い戻しの手続きをしてくれます。
そして、給与の支給時などに、高額療養費の還付分が預金口座に振り込まれるのが一般的です。
協会けんぽ・国民健康保険の場合
おもに中小企業の会社員などで協会けんぽに加入している場合や、自営業、無職、年金生活などで国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している場合は、自分で申請して高額療養費を受け取るのが基本です。
所定の申請書に診療を受けた日付、医療機関名、自己負担した金額、還付を受け取る銀行口座情報などを記入して、加入している健康保険の窓口に提出します。
高額療養費はいつ戻る?
医療費を払った後、高額療養費はいつ戻ってくるのでしょうか。
加入している健康保険による違いもありますが、受診から還付までにはおおむね3~4か月程度かかることが多いようです。
高額療養費の還付を待たずに医療費負担を軽減する方法も
高額療養費が戻るまで、基本的には受診時に医療費の自己負担を窓口でいったん支払わなければなりません。
しかし、支払いが難しいときや還付されるまでの医療費負担が重い時には、はじめから窓口負担を軽減する方法もあります。
限度額認定証
加入している健康保険であらかじめ手続きをして、「限度額適用認定証」という書類を医療機関に提出しておくと、受診時の請求額から高額療養費の自己負担限度額分を差し引いてもらうことができます。
窓口での請求額が少なくなりますので、高額療養費の申請手続きも不要です。
マイナンバーカード
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、高額療養費の自己負担限度額を超えた請求が発生しても、超えた分の請求はされなくなります。
上記に上げた限度額適用認定証も不要です。医療機関や市町村の窓口、マイナンバーカードの情報を管理するマイナポータルアプリなどで登録をして利用します。
公的制度を活用して医療費の負担軽減を
高額療養費制度では、入院費用や通院費用などが高額になったときに、医療費の負担を軽減できます。申請が必要な場合には、早めに手続きをしたいですね。
また、高額療養費の払い戻しを受けても医療費の負担が高額なときには、所得税の医療費控除で税の軽減を受けられることもあります。合わせて確認しておくといいですね。
※2024年9月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は加入先の保険制度窓口へご確認ください。
※1 出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
※2 出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用」
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。