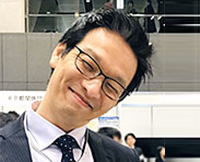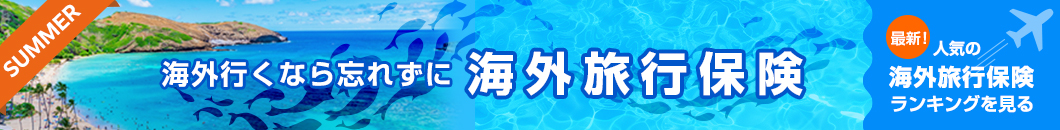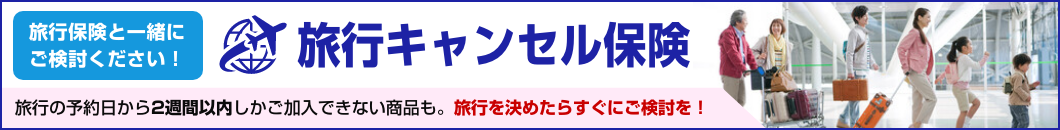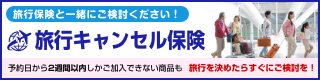医療費の負担を軽減する公的な制度には、「高額療養費」と「医療費控除」があります。どちらも医療費の自己負担の一部が戻ってくるしくみですが、どのような違いがあるのでしょうか。
医療費が高額になったときに活用できる公的制度について解説します。
記事の目次
医療費控除と高額療養費は併用できる
医療費の自己負担が高額になったときに利用できる制度として、高額療養費と医療費控除があります。この2つ制度はそれぞれ異なるしくみで、併用することができます。
そのため、高額療養費の補助を受けてもまだ自己負担額が高額なときに、医療費控除を利用できます。
医療費の負担を軽減できる公的制度
医療費控除と高額療養費は、どちらも公的な制度です。
ただし、高額療養費は公的医療保険(健康保険)、医療費控除は所得税の制度です。それぞれにおいて、要件に該当すると負担が軽減されます。
高額療養費(健康保険の制度)
高額療養費は、1か月にかかった医療費の自己負担が所定の限度額を超えると、超えた部分が戻ってくる健康保険の制度です。
年齢や所得などに応じて定められた限度額を超えた医療費を自己負担したときに、超えた金額が高額療養費として還付されます。
マイナ保険証などを利用すると、限度額を超えた医療費が請求されなくなるしくみもあります。
医療費控除(所得税の制度)
医療費控除は、高額療養費や生命保険からの給付を受けても、負担した医療費の金額が1年間で一定額を超えたときにその年の税の一部を軽減できる、所得税の制度です。
確定申告をして、税額計算のもとになる所得から、控除額を差し引きます。
高額療養費と医療費控除の違い
高額療養費と医療費控除は、医療費の負担が高額になったときに利用できるという点は共通していますが、対象になる医療費の範囲や計算方法、申請方法などが違います。
対象になる医療費が違う
高額療養費の対象になる医療費と、医療費控除の対象になる医療費には、一部違いがあります。
高額療養費の対象
高額療養費の対象になる医療費は、公的保険がきく診療の費用です。保険がきかない自費診療、先進医療、入院中の食事代や差額ベッド代、自分でドラッグストアなどで購入した市販薬などは対象外です。
また妊娠・出産費用についても、保険診療となる帝王切開は対象になりますが、正常分娩の出産費用は対象外です。
医療費控除の対象
医療費控除の対象になる医療費は、診療・治療・出産などに関わるもので、一般的に必要とされる費用です。
公的保険の対象になる医療費のほとんどは医療費控除の対象になりますが、保険診療かどうかだけが基準ではありません。
公的保険がきかない医療の一部にも、医療費控除の対象になるものがあります。
たとえば、正常分娩の出産費用、入院中の食事代、差額ベッド代のうち治療上必要なもの、入通院の交通費、治癒のために必要なものであれば薬局やドラッグストアで買った風邪薬や胃腸薬も対象になります。
申請方法・申請先が違う
高額療養費と医療費控除は、給付を受けるための申請や手続きの方法も違います。
高額療養費の申請方法
高額療養費の補助を受け取る方法は、加入している健康保険の種類などによって異なります。
基本的には、受診時に自己負担する医療費を支払った後に、1ヶ月ごとに加入している健康保険に申請手続きをして払い戻してもらいますが、勤務先が給与支給時などに精算手続きをしてくれる場合には自分での申請手続きは不要です。
また、「限度額適用認定証」という書類やマイナンバーカードを提示して受診した場合にも、請求される医療費から高額療養費の補助分が差し引かれるので、還付のための申請手続きが不要です。
医療費控除の申告方法
医療費控除の補助を受けるには、必ず確定申告が必要です。自営業などで確定申告をする人だけでなく、会社員などで年末調整を受けている人でも、医療費控除を適用するには確定申告をします。
1月1日から12月31日までにかかった医療費を自分でまとめて、翌年の2月~3月の確定申告期間に、税務署に申告します。
補助の計算方法が違う
高額療養費と医療費控除ではしくみや計算方法が異なるため、いくら戻ってくるかも違います。
高額療養費の計算方法
高額療養費は1ヶ月ごとに、自己負担した医療費から、所定の自己負担限度額を差し引いて計算します。自己負担限度額は年齢や所得(年収)に応じて決まっています。
具体的にいくら戻ってくるかは、負担した医療費の金額や、自己負担限度額によって変動します。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算は、1年間に自己負担した医療費から、生命保険からの給付金や高額療養費、傷病手当などで受け取った金額を差し引きます。
差し引いた残りのうち、原則として10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)を超える金額を医療費控除として、所得税の計算上で課税される所得から差し引くことができます。
実際にいくら戻るかは、医療費の金額のほか所得などの状況によって異なるため一概にはいえませんが、年間10万円を超えた自己負担額に税率をかけた金額が目安になります。
高額療養費と医療費控除の違い比較
※はみ出ている場合、横にスクロールできます。
| 高額療養費 | 医療費控除 | |
| 対象制度 | 健康保険 | 所得税 |
| 対象の 医療費 |
保険がきく診療のみ | 診療・治療・出産 に関わるもの (市販薬も対象) |
| 申請先 | 健康保険 | 税務署 |
| 申請の タイミング |
診療を受けた翌月 | 医療費を支払った 翌年の初め |
| 受取の タイミング |
診療月の 3~4か月後 |
医療費を支払った 翌年3~4月頃 (税額の軽減で受け取り 自体は発生しない) |
出典:筆者作成
公的制度を活用して医療費の負担軽減ができる
医療費の自己負担が高額になったときには、高額療養費制度や医療費控除を利用できます。まずは1カ月ごとに高額療養費制度を利用して自己負担を軽減し、それでも年間の医療費の負担が高額になったときに、1年分の医療費をまとめて、医療費控除を利用します。
それぞれの仕組みや申請方法を知っておくとスムーズですね。
※2024年12月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は加入先の保険制度窓口や最寄りの税務署窓口にご確認ください。
※1 出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
※2 出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。