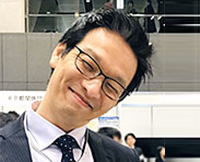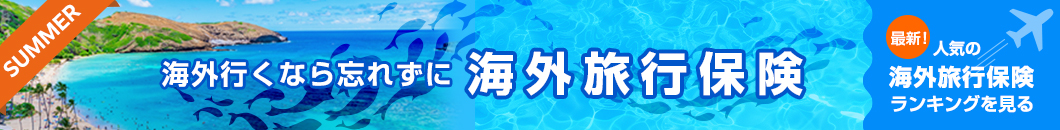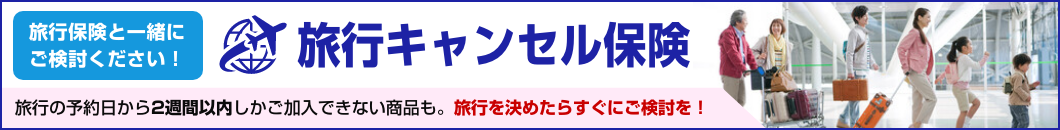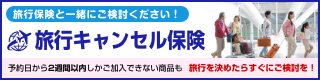子どもの教育費には、幼稚園から大学までを合計すると1人あたり1,000万円かかると言われます。
子育て支援策による補助を利用したり、計画的に積立をしたりして、無理なく準備したいものです。
教育費の準備方法や公的補助について、FPが解説します。
記事の目次
子ども1人にかかる教育費は1,000万円以上も
子どもの教育には、学校の学費や習い事、教材や文房具などさまざまな費用がかかります。
とりわけまとまった金額が必要になるのは学費でしょう。
進学先によって差があるものですが、比較的抑えられる公立でも、ある程度の負担が生じます。
すべて国公立に進学した場合でも、学費などの教育費の平均総額は幼稚園から高校までで約600万円、大学で約480万円です。19年間を合計すると、1,000万円を超えます。
子どもの教育費で受けられる公的補助
しかし、子どもの教育費の一部には、国や自治体などによる公的な補助を利用できるものがあります。
おもな制度の一例を確認してみましょう。
※地域や所得などにより、受けられる補助が異なる場合があります。
幼稚園・保育園でかかるお金に受けられる補助
幼稚園や保育園でかかる利用料は、国の幼児教育無償化制度によって負担が抑えられています。
3歳~5歳児の子どもは、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されています。幼稚園の場合は園によって利用料が異なりますが、月額2.57万円まで補助されるのが基本です。
0歳~2歳までの子どもは、無償化の対象は原則として住民税非課税世帯に限られますが、子どもが2人以上の世帯の場合は第2子が半額、第3子以降は無償になっています※。
※保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントします。
また、東京都など一部の地域では所得制限なしに第2子以降の保育料を無償化するなど、国の制度に上乗せの補助を行うところもあります。
小学校でかかるお金に受けられる補助
小学校では、一部の地域で給食費の無償化が行われています。
2023年時点では約3割の自治体ですべての小中学校の給食費が無償化されています。今後、全国的に無償化する検討も進んでいます。
中学校でかかるお金に受けられる補助
中学校では、一部の地域で授業料の補助が行われています。
東京都では都内在住で私立中学校に通う場合に、年間10万円の授業料補助を受けられます。
高校でかかるお金に受けられる補助
高校の授業料には、国の無償化制度があります。
国公立高校に通う場合は年間11万8,800円、私立高校の場合は最大39万6,000円までの授業料が実質無償化されています。
2025年4月からは所得制限が撤廃され、年間11万8,800円までは公立・私立ともにすべての高校生が支援を受けられる予定になっています。
また、2026年4月には私立高校の無償化の内容が拡充される検討が進んでいます。
大阪府・東京都など一部地域ではすでに国に先行して、所得制限なく公立・私立ともに授業料の補助が行われています。
専門学校・大学などでかかるお金に受けられる補助
専門学校、短期大学、大学などでかかるお金への補助制度もあります。
国の修学支援制度では、所得や家族構成などの要件を満たす場合に、授業料・入学金の減額・免除、返済不要の給付型奨学金を利用できます。減免や給付型奨学金に比べて利用要件が緩やかな、貸与型奨学金の制度もあります。
また、大学、自治体、公益財団法人などが独自に行う奨学金制度を利用できる場合もあります。
子どもの教育費の準備方法
教育費を家庭で準備する方法には、貯蓄性のある生命保険、預貯金、運用などがあります。
進路の希望や利用できそうな公的制度の状況に応じて検討してみましょう。
貯金
金融機関にお金を預け入れて積み立てる方法です。
普通預金や定期預金は原則として元本が保証されています※。預入金額は1円から自由に設定できます。
※金融機関の破たん時には、預金者1人当たり、1金融機関ごと元本1,000万円までと利息等が保護されます。
毎月定期的に少しずつお金を積み立てる場合には、積立定期預金や財形貯蓄制度(財産形成貯蓄制度)の一般財形を利用する方法もあります。毎月1,000円から、自由に設定した金額を積み立てます。
積立定期預金は普通預金残高から、財形貯蓄は給与やボーナスから自動的に積み立てられます。
財形貯蓄は制度が導入されている企業などに勤めている場合のみ利用できますが、積立定期預金は預金口座があれば、ほとんどの金融機関で利用できます。
生命保険
生命保険のうち、貯蓄型の商品を活用してお金を積み立てる方法です。
教育費の準備としては、学資保険、養老保険、終身保険などが一般的に用いられます。
学資保険
学資保険は、満期時に満期保険金を受け取れる生命保険です。子どもの所定の年齢や進学時などに学資金(祝金)を受け取れるタイプもあります。
保険料の一部が将来の学資金や満期金受け取りのために積み立てられるとともに、親などの契約者が万が一死亡・高度障害状態になった場合には、その後の保険料払込が免除されます。
養老保険
養老保険は、保険期間中に死亡・高度障害状態になった場合には死亡保険金、生存して満期を迎えた場合には死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れる生命保険です。
満期を子どもの入学・進学時に合わせて契約することで、教育費のための積立保険として活用できます。
終身保険
終身保険は、保険期間が一生涯続く生命保険です。
基本的には亡くなったときに死亡保険金が支払われる死亡保障の保険ですが、契約後、所定の期間経過後に解約をすると解約返戻金を受け取れます。
解約のタイミングを子どもの入学・進学時などに合わせる形で契約することで、解約返戻金を教育費に活用することができます。
ただし、生命保険を解約するとその時点で契約が消滅し、以降の保障がなくなります。また、解約時の諸条件により、払い込んだ保険料総額よりも解約返戻金などの受取額が少なくなる場合にも留意が必要です。
資産運用
個人向け国債や投資信託などでの資産運用も、教育費に備える手段の一つになりえます。
個人向け国債
個人向け国債は国が発行する債券のうち、個人が金融機関で購入できるものです。
最低1万円から、1万円単位で自由な金額を購入できます。3年満期、5年満期、10年満期から選べ、保有期間中は半年に1回、利息を受け取れます。満期を迎えると元本が戻ってきます。値動きがなく、元本は保証されています。
自動的な積立購入はできませんが、毎月新規発行(募集)しているため、定期的に少しずつ購入して積み立てることもできます。
3年~10年以内の入学・進学に合わせて活用できるかもしれません。
株式・投資信託
元本割れのリスクを許容できる場合には、株式や投資信託といった値動きのある金融商品で運用する方法もあります。
証券会社などの金融機関では、指定した株式や投資信託を積立購入できるサービスを提供しています。
また、国の投資非課税制度「NISA」を利用すれば、毎年所定の金額まで、投資によって得た利益が非課税になります。積立投資に利用できる「つみたて投資枠」の場合、年間120万円まで非課税です。
子どもの進学時期など自由なタイミングに非課税で引き出すことができます。
贈与
家庭の状況によっては、祖父母などからの贈与を教育費にあてるケースもあります。
通常、個人から財産を受けた際には贈与税がかかりますが、一定額までは非課税になるしくみを活用することができます。
教育費のためにまとまったお金を贈与する場合に利用できるのが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置※」です。子ども・孫1人につき最大1,500万円まで、贈与税が非課税になります。
※2025年3月現在、2026年3月末までの時限措置とされています。
贈与されたお金は学校の入学金、授業料、受験料、学用品の購入費、修学旅行費、塾代、習い事の費用など、教育費のみに利用できます。
この制度を利用できるのは子ども・孫が30歳未満で、祖父母などから贈与を受ける場合です。また、利用する際には初めに金融機関で申告が必要です。
ほかに、教育費に限らずに利用できる制度もあります。一般的に用いられるのは、1年間に110万円まで、贈与税の基礎控除額の範囲内で行う贈与です。申告不要で、贈与税がかかりません。
生活費や教育費として通常必要な金額を、その都度贈与する場合も非課税です。明確な非課税枠はありませんが、入学金や授業料相当の金額であれば、子どもや孫などにお金を渡しても、一般的には贈与税の課税対象にはなりません。
※贈与の時期、回数、金額などによっては、非課税とならない場合があります。また、贈与後の相続発生時に相続税の対象となる場合があります。個別・具体的な贈与の方法や課税についての詳細は、必ず税理士など税務の専門家にご確認ください。
子どもの教育のお金や備えについて、計画的に検討を
子どもの教育費は、幼少期から大学卒業までさまざまなお金がかかります。
公的な補助制度を上手に活用しながら、計画的に準備したいですね。
子どもの進路の希望や家計や貯蓄の状況などに合わせて、無理のない方法で準備できるといいですね。
※2025年3月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は地域の窓口等にご確認ください。
※この記事は2025年時点の法令等に基づいて執筆しています。内容は十分な確認を行っていますが、全てのケースにおいて上記と同様となることを保証するものではありません。個別の状況により扱いが異なる場合がありますので、詳細は相続・税の専門家にご確認ください。
※出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果について」
※出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の 非課税制度のあらまし」
-
執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。